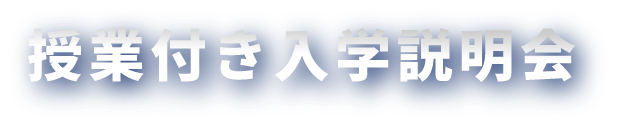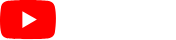【授業紹介】総合DTM作曲コース DTM・DAW
総合DTM作曲コースでは全コースにおいて、初級課程と基礎課程の2課程に跨ってDTM・DAWの授業が用意されています。
入学後に実施される入学課程判定試験の結果により、初級DTM・DAWの受講の可否が決定され、合格者は初級DTM・DAWの受講は免除されます。
初級課程 DTM・DAW
初級課程DTM・DAWでは「DTM」とはいったい何ができるのかというビジョンや概念を明確にし、DTMやDAWの成り立ちや歴史、MIDIやオーディオインターフェイスなどの周辺機器の必要性についてなど、DTMをスタートさせる前に必要となる基礎知識からはじまり、それらがどういった原理に基づいて動作しているかを学んだうえで、DTM作業が完結する一連の流れを習得し、全くの未経験者でもDAWソフトを用いて簡易な楽曲を完成させることができるようになる授業です。
初級課程DTM・DAWで学ぶ基礎的な部分をしっかりと理解しておくことで、その後に進学する基礎課程以降の総合DTM作曲コースでの高度で実践的な授業内容が、1つも余すところなく習得することができるようになり、学習効率を最大化させるための重要な期間ともなります。
現代の一般的な楽曲制作は、コンピュータ、DAWソフト、多種多様なDTM機材等を用いて進めていきます。
DAWソフトはコンピュータ上で作動するため、当然のことながらコンピュータやOSについての正しい理解が必要となり、初級DTM・DAWコースの前半の授業では、DTMやDAWの歴史を学習していくと同時に、DTMに必要なコンピュータやOSに関する様々な知識を網羅します。
コンピュータに関連する技術やテクノロジーは日々物凄いスピードで進化をし続けており、それらの延長線上にあるDAWソフトやDTM機材においても、連動するかの如く常に新しい技術が取り入れられアップデートされていますので、DTMを用いる作曲家であれば、音楽だけでなくDTMに関連したコンピュータの情報もインプットしていくことで、楽曲制作における表現のバリエーションを広げていくことができます。
また、OSをアップデートしたらDAWソフトが起動できなくなってしまったなど、最新バージョンであるが故に起こる問題もしばしば発生するため、こういったトラブルに対する調査や自己解決能力の向上にも目を向けてもらえるようになってもらい、コンピュータにおいても初心者を脱してもらうことも初級課程DTM・DAWでの目的の一つです。
基本的にDTMとは殆どの場合コンピュータとDAWソフトだけで成り立つものではなく、その他にもDTMに特化したいくつかの機材が必要となります。
例えばDAWソフトのパフォーマンスを最大限に発揮させるためのオーディオインターフェイスや、MIDI打ち込みの場面では、サウンドの確認やMIDIの入力をする際にMIDIキーボードやフィジカルコントローラーを用意しておけば、作業が非常にスムーズになり、歌手や演奏も同時にこなす作曲家であれば、自身の歌や演奏を録音するためのマイクを用意する、といったように、作曲家それぞれの表現したい音楽性によって必要となるDTM機材は千差万別となり、各々の音楽性や作曲のベクトルに合わせたDTM機材を揃えておくことで、あらゆる面で効率的にDTMでの作業を進められるようになります。
DTM機材についての授業の後半には、初めてDTMをする人達の殆どがつまづいてしまう、DTM機材を揃えた直後の初期設定について取り扱った授業も用意されていますので、どのようなニーズでの機材の組み合わせでも適切なセットアップができるようになります。
後述となりますが、機材カウンセリングという綿密なヒヤリングを経て各生徒に最適な機材をレクチャーする、授業とは別のフォローメニューも用意されています。
コンピュータ、OS、DTM機材についての基礎知識の授業を終えると、次はいよいよ実際にDAWソフトを使用した、DTMでの楽曲制作を学習する授業になります。
コンピュータの技術革新と同様に、DTMやそれに纏わる技術とテクニックは常に新しいものが登場し、黎明期からは比べものにならないほど、非常に便利で自由且つ、様々な作法やスタイルが存在するようになりました。
そうしたDTM技術の進化は、楽曲制作をする側に要求されるスキルが複雑化していっていることもまた事実ですが、初級課程DTM・DAWを受講することで、DTMの基本となる操作や概念、楽曲制作全体の大きな流れの基本をしっかり理解しておくことで、今後DTMがどのような発展を遂げたとしても、全てはそれら基本の延長線上の存在として、誰に頼ることもなく自分自身の力で問題解決をし、自由自在に使いこなしていくことができるようになります。
更に授業終盤に差し掛かると、ゼロから曲ができるまでの一連の作業をデモンストレーションで追体験できる授業が用意されており、授業で解説されているDTM作業の流れは、現在主流のDAWソフト全体でほぼ共通している内容であるため、生徒が使用するDAWソフトの種類は不問で、大きな枠での普遍的本質的なDTMの作業というものを理解してもらるような内容となっています。
初級課程DTM・DAWでは授業ごとの課題がありませんが、総合DTM作曲コースを知識的な滞りがなく受講をするための準備期間として用意されている授業ですので、各授業を通して少しでも疑問に思った際の質疑応答は勿論のこと、コンピュータやDTMに関連する概念は様々な要素が複雑に絡み合って形成されるため、授業と直接の関係がないことであっても、不明な点があれば完全に理解できるまでオンラインコミュニティにて、無制限に質疑応答を繰り返すことを強く推奨しています。
以上が授業の大まかな説明となりますが、初級課程DTM・DAWのもう1つの柱としては、授業の進行とは別に用意されたフォローメニューである「機材カウンセリング」が存在します。
カリキュラム中盤のDTM機材についての授業を受講することで、何故そのDTM機材が必要になるかということを本当の意味で理解できるようになり、不足している機材や、アップグレードすべき箇所などが、生徒自身で自然と判断できるようになりますが、これまでにリリースされてきたDTM機材は多種多様で膨大な数があり、授業を受講後即座に自身とマッチする製品を自力で探し出せるようになることは中々難しく、まだDTM機材を揃えられていない(アップグレードしたい)生徒は、機材カウンセリングにて、講師陣とコミュニケーションを取りながら最適なDTM機材の導入をアドバイスします。
よくDTM雑誌やDTM系WebサイトにてDTM機材の具体的紹介例などありますが、それらは一般論や著者によるモデルケースであることが大抵で、個々の事情を詳細にヒヤリングした上で導き出さなければ、DTM初心者ほどベストマッチとなる機材環境の構築は難しいでしょう。
初級課程DTM・DAWで用意されている機材カウンセリングでは相談者の音楽歴や予算、使用している機材を活かす方法など、生徒それぞれのケースによって最善で最良となる組み合わせを考慮し、提案していきます。
また機材カウンセリングではコンピュータの導入も手引きしており、その都度最新の情報を基に、詳細なスペックを提示、解説しながら提案しています。
オーケストラの打ち込みをメインに考えているハイスペック機を希望している場合や、持ち運びを考慮してノート型にしたいがスペックもそれなりに欲しい、などとあらゆる希望に対応しています。
尚、初級課程DTM・DAWを修了した後も、在学中であれば機材カウンセリングはいつでも受けることができます。
初級課程では課題は出題されず、授業動画を何度も復習していく中で生じた疑問を、際限なく常に対話形式で講師陣との質疑応答を繰り返していく中で、基礎知識の造成をはかっていく狙いがあります。
カリキュラムの最後に、課程終了判定試験があり、授業の理解度を測定し合格の判定が出れば基礎課程へと進むことができます。
初級課程 DTM・DAWのカリキュラム
- PCの中級者になろう
- DTMの歴史
- DTM作業場環境例
- パソコンとOSの分類
- ハードウェアとソフトウェア
- MIDIとは
- DAWとは
- DTMに必要なもの一式
- オーディオインターフェースとは
- DAWソフト紹介
- ソフトシンセとプラグインについて
- 初期設定
- 楽曲制作の一連の流れデモンストレーション
基礎課程 DTM・DAW
基礎課程DTM・DAWの授業では、DAWソフトの基本的な機能の使い方を網羅し、それらの操作を手に馴染ませ、DTMでの作曲作業を滞りなくすることで、その後に進む一般課程以降の授業にて毎授業出題される、多彩且つ実践的な作曲課題への準備を万全なものにします。
DAWソフトの機能に関する授業では、MIDIの打ち込みからオーディオ録音、ミキサー機能の使い方など、DTMの根幹と言える作曲に必要となる基本機能の全てを学習することができ、これらの内容はトラック数など機能に制限が無い、ある一定以上のレベルにあるDAWソフト全てに共通している内容であることと、実際のプロの現場では様々なDAWソフトを使用するプロが入り混じっている現状があることを踏まえ、生徒が使用するDAWソフトの種類は、シェア数が著しく少ない一部のものを除き不問にて授業を受講することができます。
基礎DTM・DAWの前半では、音声ファイルについての授業があり、音声ファイルの音質や規格について学習することで、MP3の特徴や、CDにするための規格、ハイファイオーディオなど、様々な形態を理解することで、自身の楽曲を様々な用途に活用できるようになるだけでなく、クライアントからの用途に合わせた注文にも臨機応変に対応できるようになります。
昨今の音楽業界ではデータの送受信にて楽曲のやり取りをすることが当たり前になってきていますが、多くの人がファイル送信時の基本的ルールが意識できておらず、ファイルネーミングやメールでの所作等、ビジネスマナーの点においても配慮が不足している例が多々見受けられます。
いくら楽曲は良かったとしてもこうした乱雑な仕事は、楽曲を聴く前に悪いイメージを持たれてしまい、楽曲の良し悪しとは別の次元で取引を停止される事態になることも、残念ながらしばしば散見されるようです。
これらのルール・マナーは完全に一致したシチュエーションにはなりづらいため、毎回全く同じようにとはいきませんが、本校での課題楽曲や譜面の提出を経ることで、受け取る側の気持ちを汲み取り、ビジネスマナーを意識したファイルのデータ送信を徹底していくことで、初めて作曲仕事が取れたその時から、プロの作曲家としてどこを取っても恥ずかしくな状態にまで自然と成長していることができるようになるのです。
DAWソフトについての授業では、各種機能の詳細を学ぶだけでなく、自身の良く使う機能やコマンドを分析し、それらのショートカットを駆使することで、より素早く効率的に楽曲制作を進めていくことを意識してもらいます。
これにより多くの楽曲を仕上げられるようになるだけでなく、頭の中で浮かんだ良いと思っていたアイディアが、作業にもたついている間にぼやけていってしまい、イメージをロスしてしまう、ということを防ぐことにもなりますので、作業スピードは様々な観点からも非常に重要となります。
MIDIの打ち込みについての授業では、MIDIコントローラーによる入力だけでなく、ショートカットやマウスを組み合わせた操作など、授業で解説する様々なMIDIの打ち込み方法を習得していくことで、例えば生演奏をシミュレートしたピアノのトラックはMIDIコントローラーでリアルタイム入力、機械的な4つ打ちのキックのループはマウスとコピー&ペーストを駆使した入力など、シチュエーションによって入力の方法を使い分けることができるようになります。
またMIDI編集の機能を解説した授業も用意されていますので、機械的に入力した後に、生演奏しているように編集するといった、イメージしているサウンドに近づけるため、様々なアプローチ方法を臨機応変に選択できるようになります。
プラグインインストゥルメントやオーディオ素材だけで楽曲が完成できてしまうのもDTMのメリットですが、ボーカルやギターの生演奏など、オーディオ録音を取り入れることで、自身の楽曲で表現できる幅が広がるだけでなく、ボーカルや演奏家などの協力により、自身だけでは表現できないサウンドを楽曲に取り入れることができるのもDTMの魅力のひとつです。
しかし全ての曲ごとにレコーディングスタジオを利用するといったことは予算などの問題で難しく、仮歌やギターの演奏などは、機材や環境などの条件がそろった場所での、いわゆる宅録になることが殆どとなることが実情で、オーディオ録音を多用するほど、自身でレコーディングをする機会が増えていくことにもなります。
オーディオ録音の授業を受講することで、基本となるセッティングや調整を学ぶことができ、録音時のオーディオインターフェイスの使い方や、DAWソフトの便利な機能などを理解しておけば、時間に限りがある現場などでも、滞りなく作業を進めることができるようになり、良いテイクを録れる機会が飛躍的に増えていきます。
宅録は様々な要因が複雑に絡み合い、環境作りから録音まで、すぐさま最良の実践とすることは非常に難しいですが、宅録に挑戦する際は不明点や環境作りなど、オンラインコミュニティでの質問や機材カウンセリングを積極的に活用し、知識だけでなく経験を増やしていくこを推奨します。
基礎課程DTM・DAWの後半では、DAWソフトのメイン画面の一つである、ミキサー画面の解説とトラックのルーティングについてを学びます。
DAWソフトのミキサー画面は、レコーディングスタジオにある実際のミキサーコンソールをトレースしている造りになっており、大抵の機能もそれに準じているものとなっていますが、現代では作曲を始めた時点で高性能なDTM環境を導入するケースも当たり前のものとなってきており、本物のミキサーコンソールを見たことも使ったこともないまま成長をしていく作曲家も多く、ミキサーの機能やルーティングに対する見識があやふやになりがちです。
ミキサー機能の使い方とルーティングをしっかりと把握しておくことは、プラグインエフェクトの効果を最大限に活かす事にもつながりますので、これらの知識はプラグインエフェクトの使い方やテクニックを勉強する前に、完全に理解しておく必要があります。
例えばリバーブやディレイといった空間系と呼ばれるエフェクトでよく使われるセンドリターンという手法では、センドやAUXトラック(センドトラック)の機能を用いることで、一つのプラグインを複数のトラックで共有することができ、それぞれのトラックに個別に挿入したときに比べてコンピュータへの負荷も軽く、調整も容易になるなど、使い方ひとつで非常に多くのメリットを得ることができます。
さらにDAWソフトにはオートメーションというパラメーターの自動化機能も搭載されており、トラックのパンポットやボリュームをAメロとサビで変化させたり、シンセサイザーやエフェクターのパラメーターを動的なものさせるなど、リアルの実機では非常に大変な作業も、DAWソフトでは簡単に調整が行えますので、これらの機能を使いこなすことで、自身の楽曲で効果的な演出ができるようになります。
これら授業で扱う内容で、まだ使ったことがない機能やシステムなどがある場合など、少しでも疑問に思ったことは、オンラインコミュニティ上で完全に理解できるまで、徹底的に講師陣と質疑応答を繰り返すことができます。
そして基礎課程DTM・DAWの最後には共通過程基礎修了判定試験を実施され、授業内容の理解が確認できれば、一般課程へと進みます。
基礎課程DTM・DAW に含まれるカリキュラム
- DTMで使うケーブルの種類
- セッションデータのソート
- ファイルネーミングルール
- ファイル形式と音質
- ショートカットキーの活用
- リージョンの概念と編集
- 主要な編集画面の概要
- 4つの基本MIDIパラメータ
- 4つのMIDIプログラミング
- 様々なクォンタイズバリエーション
- レコーディングの準備と予備知識
- マイクの種類と接続例
- 「宅録」の汎用例
- レコーディングの実践とモード
- プラグインの規格
- 定番メーカーとインストゥルメンツの紹介
- 基本となる4種のエフェクト
- サンプリング素材
- トラックの種類とトラックの機能
- マルチティンバー音源の活用
- AUXとバスとルーティング
- グループ機能
- センドリターンとプリ/ポストフェーダー
- パラメーターのオートメーション化
- バウンスの種類と2mixの音圧