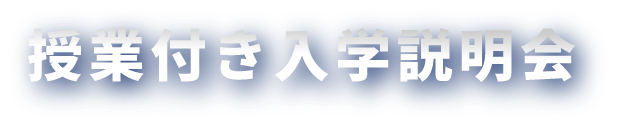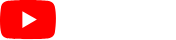様々な課題
総合DTM作曲コースにおけるユニークな課題の数々についての解説や、それらがDTM・作曲の技術向上にどのような効果をもたらすのかを解説します。
課題の種類
総合DTM作曲コースで出題される課題は以下の4つに分類されます。
- ペーパー課題
- 作曲課題
- 最近見つけたイケてる曲紹介課題
- 特別授業に関する課題
初級課程や基礎課程では、楽典や音楽理論やDTMの基礎知識を中心としたペーパー系の課題が中心となり、一般課程以降は授業内容を踏襲した作曲課題を中心とした課題に切り替わっていきます。
基本的にはどの課題もオンラインコミュニティに出題、提出のサイクルを繰り返していきます。
また、楽曲や譜面の提出は、トラックメイキングやサウンドメイキングのような、サウンドや音色作りに関する課題を除いた全ての提出楽曲について、手書きで譜表した譜面の提出が必須となります。(プロの写譜、ポピュラー科以外の音大卒等、楽譜や楽典に関する知識が既に十分にあると認められる者については浄書ソフトの使用可)
各課題概要
ペーパー課題
初級課程や基礎課程では、作曲課題は出題されず、楽典やDTMの基礎固めのための各種ペーパー課題が出題されます。
楽典では発展的な音楽理論を学んでいく上で必要となってくる度数について、最終的にストリングスカルテットのレコーディングにも通用するスコアの読み書き、他者を介した音楽において必要となる音楽通論を幅広く学んでいきます。
DTMではコンピュータやOSについての基礎知識から徹底的に理解していくことで、機材トラブルへの対応力を鍛え、将来的に数多あるDTM機材を選り分けていける概念形成をすることで、DTMに関する誤った流言飛語や過度な広告コピーに惑わされないようになります。
作曲課題
基本的には授業内容を踏襲した作曲課題が、次回授業を提出期限として出題されます。
作曲や音楽理論系の授業、DTMやトラックメイキング系の授業どちらにも出題され、カリキュラム初期の頃は8~16小節程度の小曲の習作が中心となりますが、授業が進むにつれて徐々に長尺、複雑化していき、終盤ではいよいよフルコーラスやそれに近い楽曲を作曲していくこととなります。
授業で学んだ技術や用法を盛り込んだ楽曲の作曲を、概ね8小節~16小節の範囲にて指定され、手書きによる譜面の提出もセットとなります。
- メロディライティグ作曲課題
- 授業で扱ったコード進行、ハーモニーを楽曲内に再現する作曲課題
- コード進行を変化させずに別メロディをのせる作曲課題
- メロディを変化させずに別コード進行を展開する作曲課題
- 1つのメロディで複数のジャンルの楽曲制作をする作曲課題
- 様々な転調を用いた作曲課題
- 例示された楽曲を別ジャンルに編曲をする作曲課題
- 指定されたシンセサイザー音色を再現する課題
- 指定されたビートトラックを再現する課題
- 同じEDM楽曲を2012年と2020年と別アレンジで作曲
- 例示された映像作品のSEやジングルを制作する作曲課題
- 例示された映像作品のBGMを制作する作曲課題
等々。
上記は作曲課題の一例ではありますが、生徒個人の目指す目標や苦手箇所の露見などにより、個別に最適化された作曲課題が出題されていくこととなり、これらの措置は個別受講だけでなくグループ受講であっても同様となります。
個別受講においては課題の合格をもって次の授業に進むことができ、直近2回分の課題の不合格が続いた場合は新規授業の配信を停止し、まずは課題の合格を最優先とし、学習進行上特に重要なマイルストーンとなる授業が反映された課題が不合格の場合は、即座に新規授業の配信停止がとなり、復習と課題再提出となることもあります。
グループ受講においては次回のグループ授業までに間に合わせるように合格しなければならず、個別受講よりもやや時間的な締め切りが設けられています。
最近見つけたイケてる曲紹介課題
毎週1曲をノルマとした最近リリースされた楽曲を、作曲家としての立場から様々な角度で分析した感想と共に、オンラインコミュニティに投稿する課題です。
日々大量の楽曲をinputすることを前提としており、生徒講師陣の垣根なくそれらを発表し合っていきます。
当課題の必要性は本ページ下部に理由を記してあります。
特別授業に関する課題
総合DTM作曲コースのカリキュラム終盤に用意されている特別授業での作曲課題です。
- コンペ実習にて出題される実際のメジャーコンペと同一オーダーの作曲課題
- ストリングス講座のための弦楽四重奏曲の作曲課題とディレクターとエンジニアに渡すスコア、演奏家に渡すパート譜
- CM、ゲーム、劇伴等映像音楽実習で使用する楽曲の作曲課題
- レコーディング・ミックス・マスタリング講座のための作曲課題
これらの課題はフル尺で提出する作曲課題となり、加えてどの特別授業も実際の現場で行われたことを題材としているため、それまでの学習の集大成となる授業となっています。
課題が必要な理由
DTMや作曲技術の向上において最も効果的なことは、ピンポイントにテーマやお題を定め、指導者からの助言を得られる環境下で、沢山曲を作っては反省やブラッシュアップのサイクルを繰り返していくことであり、プロとして活躍するどの生徒にも共通することでも証明されている、開校当初から一貫した理念でもあります。
課題の中でも特に重要度の高い、「作曲課題」と「最近見つけたイケてる曲紹介課題」の2つについて、その必要性に迫ります。
音楽を作っていく作業とはinputとoutputの繰り返しです。
そして「作曲課題」とはoutputに、「最近見つけたイケてる曲紹介課題(以下、イケ曲課題)」はinputに、置き換えることができます。
通常音楽学校が提供するinputとは、授業を通したカリキュラムや指導になりますが、そうした教育だけでは、音楽理論や機材にだけ異様に詳しいものの作曲数が極端に少ない、悪い意味での上級者ばかりが生まれてしまうこれまでの悪しき循環を断つことができません。
様々なジャンルや使用シチュエーションを持つ音楽が、今現在どのような方向に向かっているのかを、常に沢山の新たな楽曲を聞いて把握することだけが、耳の解像度の向上と、今の世の中が是とするサウンド全体の流れについての耳の更新が行える唯一の方法です。
現代的な楽曲のテイストを感じられる要素はメロディやコード進行よりも、圧倒的にサウンドやアレンジやミックスの占めるウェイトが大きく、しかし曲全体で聞けば今っぽいとか古臭いとかいう感想は誰でも持つことができるものの、1つ1つのトラック自体のサウンドの差は非常に小さく些細なものになり、それらのトラックのバランスの取り方や混ぜ方は更に繊細な作業となります。
音楽以外のどんなことでも同じですが、サンプル数が少ない状態では大雑把な比較しかできず、細かな違いに気付くことはできません。
幅広く雑多な沢山の音楽のinputを怠った人間は、その極僅かな差異について、何が違うのかを聞き分けることができず、どれだけDTMや機材に詳しかろうが、そもそものサウンドのチョイスが成功せず、また成功していないことに気付くこともできず、そうしたトラックをいくら上手くミックスできたところで、到底世間に受け入れられる楽曲にはなりません。
これはアマチュアだけでなく、著名なプロであっても全く同様であり、inputを怠った人間から脱落していきます。
要点としては、個人の趣味趣向の延長ではなく、現代の音楽シーンのマーケティングリサーチの一環として、とにかく幅広く行っていくことです。
何よりもある作曲家からすれば、最新の楽曲の作曲者とはライバルであり同業他社であり、我々が最も注視し意識しなければならない分析対象です。
その世界に進もうと思っているのであれば、まずはそうした競合調査やマーケティングを行った上で対策を立てねばなりませんが、それすら行わずに目指すというのは実に合理性に欠けます。
わざわざ主張する必要もないあまりに当たり前のことであっても、こと音楽になると正しい判断ができない例が後を絶たず、これではそもそも挑戦する土台にすら立てていない状態です。
本校生徒においてはこうした事態に決して陥らぬよう、学習の進捗に関係なく入学時からイケ曲課題を行い、生涯に渡って当たり前の日課となるように積み重ねていきます。
また、在校生講師陣全員で投稿していくため、他者の考察や分析も学ぶことができ、高度な情報交換の場ともなります。
inputの準備が整えば次にoutputです。
outputとは当然作曲をしていくことに他なりませんが、どんな高等な内容であってもただ授業を聞いているだけでは作曲技術の向上は望めず、授業内容に応じた作曲課題の提出楽曲を講師陣が精査することを都度繰り返していくことにより、授業の理解度を判断していきます。
ただ闇雲に思いついたままに作曲を繰り返しても、スキルの向上という点において効果は薄いと言わざるを得なく、習得したい技術ごとのテーマを絞り、講師陣の指導を受けながら試行錯誤を繰り返すことで、思い通りに使いこなせる本物の技術として、自分の中に落とし込んでいくことができるようになります。
課題内容もメロディ、トップライン、コード進行、転調、モード、和声学等の主に譜面に書き表すことができるものと、シンセサイザー、トラックメイキング、ミックス・マスタリング等のサウンド面での作曲とに大別でき、それぞれのテーマにおいて様々なオーダーが出されます。
オーダーが多岐に渡る理由は、プロとして活動していく上で作曲技術以外の様々なスキルも磨いていく必要があるためです。
実際の仕事においては、クライアントからの様々な要望に的確に応えていかなければならず、相手の立場に立ったものの見方ができなければ、そもそも仕事を継続していけないという、社会的な当たり前の理由があります。
ただ単に良い曲が作れるというだけではプロとしては不十分で、クライアントが何を求めているのか、オーダーシートやヒヤリングの中から見つけ出す能力がなければ、いくら素晴らしい作曲能力があっても全く役に立ちません。
そして締め切りに間に合わせて曲を仕上げることへの慣れや、作業スピードの速さも求められます。
それ以外にも、相手の要望するフォーマットや方法にて提出の体裁を整えたりなどの事務作業も、音楽の仕事を’継続’して獲得していく上で重要です。
特に事務所に所属せずフリーで活動する場合は、本来マネージャーが行ってくれる仕事まで自分でこなしていかなければなりませんので、在学中に社会的な広義なものから、音楽業界独自にローカライズされたルールやマナーまで学ぶことで、自己解決能力をより高めていきます。