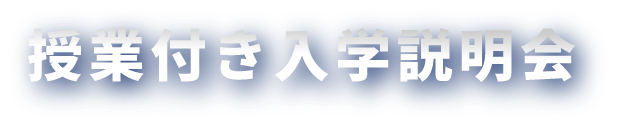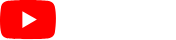校長挨拶・学校理念
当ページをご覧下さり有難う御座います。
東京DTM作曲音楽学校長、donsukeと申します。
こちらの挨拶文を初めて書いたのが2013年末。
そして2021年5月のリニューアルの際に初めての改稿を行い、1年余りを経て今回で3回目の書き直しとなりました。
前回のリニューアルがVer1→Ver2へのアップデートだとすると、差し詰め今回はVer2.5くらいになると思いますので、前回したためた内容を編集、加筆という形でのご挨拶とさせていただきます。
2014年に本校が巻き起こしたこと
東京DTM作曲音楽学校は、他校とは一線を画した、それまでに類を見ない数々の革新的なコンテンツを掲げ、2014年初に開校しました。
当初異彩を放っていた本校のカリキュラムや指導理念が本質的価値を持つものであったかどうかは、少人数制だったにも関わらず今や音楽業界で大活躍する卒業生達の実績や人数が全てを物語っています。
その後、本校の示した革新性は瞬く間に浸透していき、今や多くの他校やスクールが本校の授業や方針を取り入れざるを得ないまでに一般化を果たしました。
何時まで経っても悲痛な想いで真剣に学びたいと願う生徒側の目線に立った教育を行わないDTM、作曲教育業界全体を、次のステージへと押し上げるきっかけになれたこと、並びに当初は斬新に映った授業がコモディティ化にまで至ったことは、僭越ではありますが一定の達成感を覚えております。
輝かしい実績を残す卒業生達を数多く輩出できたワケ
何故本校は、短い間に他校と比較にならない割合で、プロの作曲家として活動をする卒業生を多数送り出すことができたのかといえば、たまたまそうなったという訳ではなく、予めそうなるようにデザインした上で立ち上げたからに過ぎません。
まずは講師陣と経営判断
音楽大学や専門学校では当たり前となっているレッスンプロの採用をなくし現役プロフェッショナルだけで講師陣を構成しました。
こちらに関してはあまり説明の必要はないかと思いますが、8合目までしか登山をしたことのない人間が登頂までの道程を教えられないことは当然なものの、残念なことに音楽教育の世界ではこれがまかり通っており、殆どの学校やスクールが上級者までしか生み出せない原因がここにあります。
趣味の延長線上に対してであれば問題ありませんが、音楽大学や専門学校にまで通って作曲を学ぼうとする程の強い気持ちを持った者達に対して、プロの現場で行われている実情とあまりにも掛け離れた内容の教示の常態化を、まずは正さねばなりませんでした。
またこれから学校を選ぼうとする方には非常にわかりづらい点の1つとして、プロの現場を取り巻く様々な内容は時代によって大きく異なり、特に近年における変化の幅は加速度的に広まっていっていることからして、現在も現役のプロフェッショナルとして現場に出続けているかどうかということは、非常に重要な判断指標となります。
次に重要なことが、カリキュラムや学校システムの決定者です。
大抵の学校やスクールでは、いくら素晴らしいカリキュラムや指導力を講師陣が保持していたとしても、実際にそれを学校のシステムに採用するかどうかは、非音楽家である経営者ができるだけ抑えた予算の中で決定していくことになり、それではどうあがいても生徒にとって最良な施策を講じることはできません。
プロになるために本当に必要なカリキュラムが何なのか、といった点から出発することでしか生徒にとっての最良の学校を作ることはできず、そのためには最終的な決定権を私が持つ必要がありました。
次にカリキュラムの策定
プロとして着実な活動するために何が必要なのか、という着地点から逆算して導き出すことで、1つの無駄もなく、限られた時間を最大限活用できるように、徹底的に合理的に組み上げていきました。
例えば、限られたプロしか出入りしない最高峰のレコーディングスタジオにて、プロオーケストラ首席奏者の講師達が全生徒の自作曲をレコーディングするという授業は、一見突拍子もないことのように映るかもしれませんが、プロとして活動していくということはそういった現場を仕切れて当たり前であり、講師陣全員が普段からそういった現場で仕事をしている以上、その必要性は極自然と思い付いたに過ぎません。
上記は本校の授業の一例ですが、どのような授業にもこうした、「仕事をする上で」という他校ではまず設定されない高い視点からの工夫が凝らされていることにより、各授業には沢山の要素が詰め込まれることとなり、結果的に尋常ではない密度と速度で展開することとなり、毎回の授業が戦いのような張り詰めた緊張感の中で進行していくこととなりました。
そして、指導理念と指導法
単に教え方や説明の上手さだけの追求では、上記の内容を伝えきることはできません。
教育論や指導に関するに最新の研究や理論を、DTMや作曲の教示という非常に特殊なテーマでローカライズを施し、前項で策定したカリキュラムをいかに短い回数と時間で、理解できるものへと昇華させられるか、絶えず追究を続けています。
時にあやふやで抽象的な伝え方になってしまいがちな、DTM、作曲の指導では、誰が聞いても一定の理解ができる段階にまで言語化を行い、手法の再現性が高くなければ、本当に生徒自身に根付くスキルとして活用していけるものとはなりません。
よくある著名人の楽曲制作の解説シーンやトークセッション、作曲スキルのない音楽業界人によるアドバイスなどは、受講者が自身の楽曲にそのエッセンスを反映させることは非常にハードルが高く、既に同一レベルのスキルを持つ人間でないと難しいことが殆どでしょう。
何故ならば、音楽とは1曲ごとにそれぞれ異なった要素の集合体が1つの方向性を目指すことで成り立っており、ある楽曲の解説を詳細に聞いたところで、他の楽曲にその手法や方法論をそのまま転用しても成功することはまずなく、プロセス1つ1つに対して何故そうした選択したのかという根源的な部分への理解がなければ、手法を習得したことにはならず、自作曲へのフィードバックもできないままです。
そうした理由から、楽曲内に狙い通りの手法をしっかりと再現していくための指導法の確立は絶対となり、最短で深い理解に繋がる様々な施策を、随所に設定しました。
熱意の高い生徒だけが集まる場を作る
ここまでは授業や指導に関する仕組みやフォーマット作りについての話でしたが、これらの仕組みは真剣でひたむきに頑張ろうとする熱意のある生徒達がいて、初めて意味を持ちます。
残念ながら、わざわざ専門学校や音楽大学に進学してもなお、ひたむきに頑張る者を揶揄したり馬鹿にする風潮は多かれ少なかれ存在し、それらは全体の士気の低下となってその場にいる者全員に大きな悪影響を及ぼします。
そこで本校が目指したのは、「本気で頑張ることが普通で当たり前」雰囲気、風潮を作り、そうした志向を持つ人達だけが集まる場を作るということでした。
しかし、口で説明する分には簡単ですが、実際にそういう高い熱意を持った人達だけを集めることはとても難しく、それを可能にしたのが、今や伝説となった超長時間(半日以上開催することもしばしば)に及ぶ入学説明会での、時間と内容に制限がない模擬授業でした。
HP上だったり、1、2時間で終わる学校説明では、いくらでも表面上の体裁を取り繕うことができます。
しかし、時に昼の15時から翌朝の始発までという尋常ではない長さの授業では、時間が経つほど表面的な会話はなくなり、誤魔化しの一切効かない素の部分まで曝け出さざるを得ない状況となり、既にプロとして活動するレベルの参加者も多い中では、上辺だけの知識や能力ではすぐに見抜かれ、一方で参加者のほうはその熱量や細部にまで及ぶ話についていけない者は途中で退席します。
そして、本当に幅広く音楽に関するあらゆるテーマについてとことん話し合い、参加者の疑問に核心を突いた回答を繰り返していく中で、我々の持つ高い指導力と膨大な音楽知識や、異様な熱量が伝わり、それに共感できる感度を持った参加者だけが、最後まで残ることとなったのです。
こうして、やる気と熱意に満ち溢れた生徒達だけが自然と集まる場作りをかなえ、偶然ではなく当初の想定のとおり、本校はセンセーショナルなスタートを切ることができました。
やる気がある生徒達しかいなかったからこそのもどかしさ
説明会での白熱した熱気は当然受講が開始してからも引き継がれ、同期生徒全体伝播するだけでなく、相乗的に高め合っていくこととなります。
旧本科では第1回目の授業から最終回に至るまで毎週作曲課題が出題されていましたが、特に顕著だったのが作曲課題における「素晴らしい意地の張り合い」です。
授業内容に連動した作曲課題ですので、曲作りにおける指示や制約が多々ある中で、課題という域を遥かに超えて全身全霊を込めた楽曲を提出する生徒が必ずおり、それに触発された他の生徒達が、次回の提出曲を同じくらい全力で仕上げてきた、などということをよく目にしました。
しかし、そうしたやる気や刺激の与え合いが相乗的な効果を生む素晴らしい環境は、一方で贅沢な悩みも生み出すこととなります。
先ほど戦いのようなと例えましたが、生徒達が醸し出すもっと知りたいという学習意欲に対する張り詰めた緊張感は凄まじく、授業内やオンラインコミュニティにて行われる質疑応答は、授業で扱う内容の枠を超えた、縦横無尽な音楽に関する極めて多彩な内容に満ち溢れ、どれだけ沢山のことを彼らとやり取りしたか計り知れません。
そうした素晴らしいやり取りの蓄積は、その反面で6ヶ月という限られた在学期間内に共有すべき情報量が、期生を重ねる度にどんどんと増えていくこととなり、我々のモットーの1つである、有益な情報を期生に関係なく全員で共有していくことが、いよいよ物理的に厳しくなってきたのです。
我々はもう1度、DTM作曲教育に革新を起こします
そこで遂に、通学/スクーリングというスタイルを撤廃し、授業の大部分を動画化してオンライン受講を基調とすることで、有益なコンテンツを余すところなく全生徒がそれぞれに最適なタイミングでアクセスできるように、全面的にリニューアルするという決断を下しました。
動画化をすることで質を落とさないまま授業量を増加させることができ、学習時間、学習サイクル、学習地域、更には入学時期も、完全に生徒個々の都合に合わせて設定できるようになりました。
それにより、DTM、作曲の技術向上にとって最も重要である作曲課題に対して、我々講師陣の指導リソースをより充当することができるようになったため、更に詳細なテーマに広げて課題の拡充を図り、より一層生徒1人1人に寄り添った指導の充実を図ることができました。
その他、リニューアルに関する内容は是非詳細のページをご覧下さい。
当然といえば当然なのですが、プロになり結果を出している生徒達は皆一様に作曲数(output)が多く、習作の数こそ成長の土台であることは彼らの実績が証明しています。
しかし、ただ闇雲に数を作ればいいというわけではなく、まずはoutputの元となる良質なinputを日々大量に続けた上で、1曲ごとにどのような使用想定の楽曲であるかピンポイントにテーマを定めて作曲をし、指導を通してその楽曲の反省点や改善点を導き出し、次の楽曲においてそれらの改善点を盛り込んだ作曲し、以降指導と改善と作曲を繰り返していくことで、作曲におけるPDCAサイクルを正しく回していくことができるのです。
指導者がいることの本当の価値とは、知識や技術の教示だけでなく、生徒自身が掲げた目標や方向性に沿った形でブレのない成長をしているのか、提出された楽曲をコミュニケーションを取りながら丁寧に指導していくことで、その目標達成をどれだけ早く実現させてあげられるかにあります。(仮に指導者がいて沢山の楽曲を作曲しているにも関わらず、結果が伴わないのであれば、指導者を変更を検討すべきでしょう)
そして、それらをより確実に実現していくためには、画一的な指導でなく、個々の得手不得手を前提にした、パーソナライズドされた個別の指導が必要であり、作曲課題のバリエーション展開と楽曲指導のリソースを大幅に増加させられたことで、更に生徒の成長速度を加速させることができました。
・・と、ここまでが、2021年5月時点でのVer2のリニューアル内容です。
東京DTM作曲音楽学校Ver2.5
そして2022年8月、満を持して更なるリニューアルを行いました。
大きくは2点に集約されます。
1つは、コースが増えたことです。
2021年のリニューアルでは、生徒個々が自分の望むペースで学習を自由に制定し、講師陣においても生徒個別に最適な指導方針を制定できるようになりましたが、この新システムを踏襲しつつ期生制度/グループ受講を復活させました。
オンラインコミュニティや毎月開催される要登校のスタジオ実習授業にて、生徒や卒業生同士の縦横に至るコミュニケーションは確保されていますが、共に切磋琢磨する同期生の存在がより高いモチベーションに繋がる方も一定数いることを鑑みて、自分の特性に合わせてより最適なコース選びができるようになり、より多くのニーズに対応できる形となりました。
2つ目は教室を撤廃し、最先端且つ最高な環境のスタジオに改装をしたことです。
授業の殆どオンライン化したとは言え、自由参加の登校授業は毎月ありますので、生徒を受け入れる設備は必要ですが、他校のような1人1セットの簡易DTM環境は全く必要ありません。
これだけ多くの音楽大学、専門学校卒の人達が、未だに誤った機材の情報に翻弄され、プロが作り出すサウンドの足元にも及ばないサウンドしか作れない現況は、いかに授業の中でそうしたリアルを教えることができていないかというバロメータであり、ネットや雑誌での言説に惑わされない、本当に現場で重宝されている機材や用例、最先端のサウンドに触れられる機会を用意することこそ、この情報過多の時代において学校が果たすべき義務の1つであり、本校でしか伝えることのできない優位性の1つでもあります。
東京DTM作曲音楽学校のこれから
今回のリニューアルは、小さなことから大きなことまで学校の隅々に、今まで以上に軽快なフットワークで日々様々なアップデートを加えていくことができるようになった象徴的な出来事でもあります。
昨今の社会的な変化の加速度の中では、時代へのアジャストを前提とした常に変わり続けていく姿勢こそ、むしろ普通のスタンスであると言っても過言ではありません。
歴史と実績を重ねたことによるアドバンテージは、既に醸成された学校風土が周知できていることで、本校を本当に必要とする人がより迷わず見つけ出せるようになり、初めて本校にコンタクトを取った際もより本質に迫ったコミュニケーションが取れることに繋がります。
そして、次項に続きます。
音楽学校は無くなります
音楽とは最早それ単体で存在しているわけではなく、インターネットを中心としたテクノロジーの進化との親和性が高く、いずれこうした舵切りをすることは開校当初から織り込み済みです。
そして、想定の最終地点は、そう遠くないうちに学校事業を畳むであろうということ。
新旧の価値観やテクノロジーが汽水域のように入り混じる今日では、次を読む力が何より大切です。
何故ならば、音楽や音楽を取り巻く環境や価値観は、数百年間あまり変わらないことから、数ヶ月単位で変わってしまうことまで、その要素ごとに大きく異なります。
なんでもかんでも新しくても上手くいかないし、古いままというのももっての外。
これは音楽教育に限ったことではなく、社会情勢、テクノロジーの進歩、世界的な意識の移り変わりを鑑みれば、これまで不動で普遍のように思えていた教育そのものの在り方が終焉を迎えようとしていることは明白です。
初めから終了することを考えて開校するというのは、一見ネガティブに映るかもしれませんが、これまで当たり前だった教育の終了が意味する未来とは、生まれや境遇による教育格差がなくなり、本人のやる気次第でどんなことにでもチャレンジのできる、実に素晴らしい時代の訪れでもあります。
最後に
5年後、10年後、それがいつになるのかはわかりませんが、日々のアップデートを欠かさず重ねていくことで、そうした兆候は必ず読み取ることができます。
そして、本校を立ち上げた時と同じように、世の中が必要する役割を誰よりも早く見つけ出し、次の時代を切り開いていく指針となり続けていきます。
もちろん、プロフェッショナルな音楽家として常に戦い続けていくことを土台としながら。
音楽と世の中が今後どうなっていくのか、そしてそこに我々がどういった形で携わっていけるのか、とても楽しみで仕方がありません。
一生を音楽と共に歩んでいく同志として、皆様と共に切磋琢磨していくことができれば幸いです。
東京DTM作曲音楽校長 donsuke